なかのひと vol.1
なかのひと vol.1
土木事業本部 主任 M
現場 佐賀208号川副IC橋下部(A2)工事

中野建設のことは、中のひとに聞く!
「なかのひと」では、入社1年目・建設業未経験の広報担当Wが中野建設で働く“中野建設の人/中のひと”の魅力を伝える現場取材企画です。
第一弾は、土木事業本部の現場を取材しました。
佐賀平野のまんなかで
11月上旬、佐賀平野の真ん中にある川副ICの現場に伺いました。
隣接する工事の業者さんが多く行き交い、現場は朝から活気に溢れていました。
この日お話を伺ったのは、土木事業本部 主任Mさん(31歳/中途/4年目)。
先日まで、有明海沿岸道路の「川副IC」橋下部工で現場代理人を務めていました。
取材を行ったのは完工前後の忙しい時期でしたが、落ち着いた表情で丁寧にお話してくださいました。
「地元で働きたい」という想いから
M主任は小城市のご出身。高校までは柔道に専念し、地元の大学に進学後は建築やダム周辺の環境に関して学んだそうです。卒業後は広島に拠点を置く上部工専門の建設会社に新卒で入社。主に九州圏内の橋梁工事に5年間従事したのち、中途採用で弊社に入社。
入社の決め手は、ライフステージの変化に伴うものだったそうです。
「結婚を機に、故郷佐賀で働きたいと思うようになりました。そんな時、地元で働く先輩から中野建設を紹介してもらったんです。」
「小さい頃から馴染みのあるこの街に自分の造ったものが出来ていくのが嬉しく、この場所で働く魅力の一つだと思っています。」

入社以降、一級河川の堤防工事やサンライズパークの外構工事、そして現在の川副ICと、さまざまな現場で着実に実績を積み重ねています。
現場で学ぶ、現場が育ててくれる
M主任の担当されていた「川副IC」は、有明海沿岸道路の「諸富IC」から西へ続く区間のひとつです。北部九州の有明沿岸部をつなぎ、既に開通している区間を含め、渋滞の減少や交通サービスの向上などの効果が期待される有明海沿岸道路。鋭意工事が進められている国交省管轄の現場ともあり、隣接工事の業者さんが(取材当時)10社ほど入る複雑な環境の中で、日々工事が進んでいます。

この現場特有の難しさなどあったのでしょうか。
「工程の中で、というよりも隣の現場との調整や、工事車両の動線をいかに効率的にするかを常に考えていました。自分の現場だけを見ていても成り立たない現場なので、周辺環境との関係づくりを特に意識しています。」
因みに、M主任が“下部工”の現場代理人を務めるのはこれが二現場目。
そもそも下部工とは、“橋の足にあたる部分(の工事)”で、基礎、橋脚、橋台の工事を主に行います。この3つが揃ってはじめて、“上部工”をどっしりと支えることができます。

地盤が軟弱で沈下しやすく、冠水なども頻発するこの佐賀平野では打設精度の確保が非常に難しく、下部工の施工管理は一流の技術が必要な土地です。
佐賀平野では支持層(硬い地層)がとても深い位置にあり、その分、杭は長くなります。そして杭が長くなればなるほど「垂直精度」や「貫入深度」の管理が難しくるとのことで…。ちなみに今回の工事での杭長は、およそ40mだそうです!
“下部工2回目”のM主任、「まだまだ知らないことばかり、早く先輩みたいになれたら」と微笑みながら語り、私の素人質問に対しても真摯に一つひとつ受け答えするその実直な姿勢にリスペクトが爆発!さらに根掘り葉掘り教えてもらいました。
そもそも橋脚は左右で役割が異なり、「fix/move」の仕組みがあることなど、普段何気なく使っている橋は奥が深いという大きな気づきがありました。
尊敬できる先輩たちがいる
中野建設に入ってまず驚いたのは、先輩方の技術力と人間力だったそうです。
「(先輩方が)本当にすごいです。経験と知識に裏打ちされた、いい意味での余裕があります。もちろん、責任の伴う業務ですから厳しさはありますが、同じ視点に立って考えてくれて、学びを得やすい雰囲気があります。」
現場ごとに指導してくれる先輩が替わるため、学びが絶えないとのこと。
「“この人はこう言うけど、あの人はこう考えている。それらを踏まえて自分はこう思う”。
そんなふうに、自分の考えを持ちつつ、いいところを吸収するようにしています。」
「まずは自分で調べてみる」
仕事の進め方について伺うと、M主任は少し考えてからこう話してくれました。
「まずは自分で調べて、それでも分からないことは先輩に聞くようにしています。
ただ聞くだけではなく、自分なりに考えた上で聞くことを大切にしています。」
「そういった積み重ねで、天候による工程のずれなど臨機応変な対応が求められる時でも、
冷静に工程を組み直すことができるようになりました。」
身体と頭をフル回転させながら、日々現場と向き合っています。
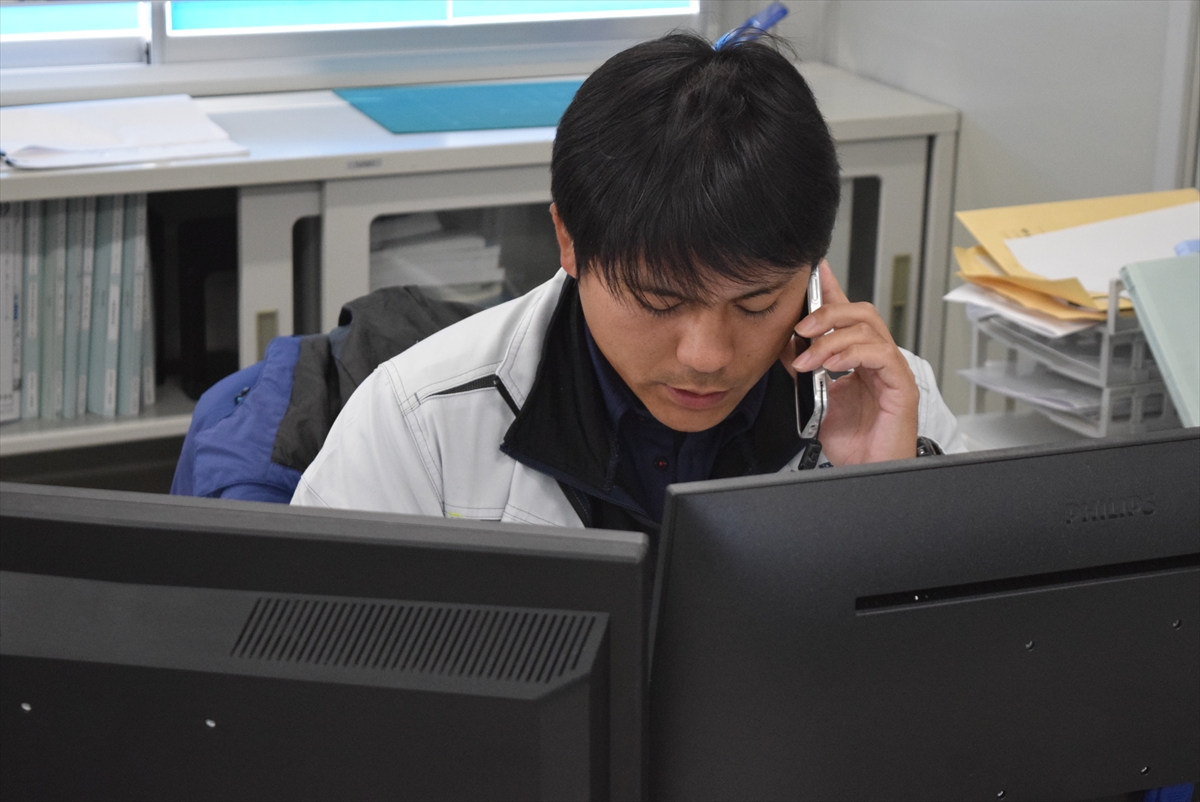
自分のつくったものが、佐賀に残っていく
「自分の住む街に、自分の造ったものが残る。それがいちばんのやりがいです。」
そう話すM主任の表情には、穏やかな誇りが滲んでいました。
休日には家族と出かけることも多く、取材週には「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」や「唐津くんち」に行かれたそう。仕事もプライベートも、故郷の風景とともにあるようです。
これからの目標
「これからは、先輩方のように技術力と人間力をもっと高めたいです。
作業員さんとの関わり方や行政の方など発注者とのやり取りも、まだまだ学ぶことばかりです。」

また、M主任は若手社員の“これから”にも寄り添っています。
現在、土木事業本部では、入社して間もない社員と上長との、月ごとに工事ステップの振り返りを行う機会を設けており、「(若手社員が)“今なにをすべきか”を考えて動けるようになってきている」と話していました。
「経験を積めば自信になる。だからこそ、どんどんトライしたり、分からないことはそのままにせず声をかけてほしいですね。」
一緒に次の世代を担う“仲間”として、後輩技術者への思いを語ってくれました。
最後に
取材の最後に、「仕事で大切にしていることはありますか?」と尋ねたところ、M主任は少し笑って、こう答えてくださいました。「できることを淡々とやることです。分からないことがあればそのままにせず、理解できるまできちんと聞く。それを積み重ねることが、現場を動かす力になると思っています。」
その言葉どおり、M主任の仕事には、静かな熱意と誠実さが感じられました。
佐賀の街に、彼の手がけた橋が立ち、これからも地域の暮らしを支えていきます。
ものづくりの技術だけでなく、人を大切にする姿勢や、誇りをもって地域に向き合う姿勢。
それこそが中野建設の魅力のひとつだと、取材を通して改めて感じました。
末筆ながら、第一弾の取材に快くご協力いただいたM主任、そして本企画の立ち上げにご支援くださった本部長方に、改めて御礼申し上げます。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。次回もぜひお楽しみに。
中野建設 W
